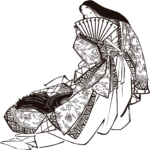春日局は家光の実母だった!? 次期将軍をめぐる実母・お江との激しいバトルの裏事情
日本史あやしい話
■国松を溺愛する実母・お江に敵対
一方、お江はといえば、こちらは戦国大名・浅井長政の三女で、佐治一成と結婚していたものの、秀吉の命によって離縁させられた上、秀吉の甥にあたる豊臣秀勝と再婚。秀勝が急逝するや、今度は、徳川秀忠と結婚させられたという女性であった。武家のしきたりとはいえ、本人の思惑など何するものぞ、政略の一環として、まるで心など持たぬ物かのようにやりとりされたのだから堪らない。それでも、秀忠との間に、家光や千姫、忠長など2男5女をもうけているから、それなりに仲が良かったというべきだろうか。こればかりは、幸いであった。
ただし、竹千代を実質上、乳母に取られた形となったことを悔やんだからか、その弟・国松は、自ら手をかけて育てたようだ。それゆえに溺愛の度合いも半端ではなかった。危惧した家康から訓戒状を渡されるほどだったとか。そればかりか、竹千代を育てるお福と対立。重臣たちの間にも、竹千代派と国松派に別れて派閥争いを演じるなど、良からぬ空気が漂い始めたのである。
困ったことに、家光の容貌は今ひとつで、病弱で吃音という不利な条件が揃っていた。他方、国松は容姿端麗で才気煥発だったというから、誰が見ても国松の方が優勢であった。これを憂慮したお福、何と伊勢参りを装い、駿府城にいた大御所の家康のところへ駆けて直訴したという。このあたりも、真偽のほどは別としてよく語り継がれるところである。
もちろん、竹千代を世継ぎにしてくれるように懇願。これが家康の心を動かしたものかどうかは定かではないが、江戸城において、長幼の序を明確にした一連の動向を目に浮かべる方も少なくないだろう。いわゆる、「家康が竹千代を上座に座らせた上で、つられて上座に上がろうとした国松を叱咤した…」云々である。お福が、お江に勝利した瞬間であった。こうして長子相続のルール、すなわち竹千代が次の将軍になるということが、家康のツルのひと声で確定したのだ。
この時下座に座らされた国松こと忠長は、後に甲府や駿河、駿府に至る計55万石の大大名となるも、乱行奇行がたたって改易。最後には切腹させられてしまった(1633年、享年28)というのも、悲しい結末であった。
最後に大奥のことにも触れておこう。大奥の制度が整い始めたのは、お江が亡くなり、お福が春日局として実権を握ってからのことである。元々お江は側室の制度が大嫌いで、当時の大奥には一人の側室もいなかった。これに対して春日局は、家光に世継ぎが生まれることを最優先。身分の違いをも顧みず、側室にふさわしい女性、早い話が、よく子を生みそうな女性を数多く集めたことが始まりであった。父が禁猟とされていた鶴を撃ったことで死罪となったという農民の娘・お楽(四代将軍・家綱の生母)や、八百屋あるいは畳屋の娘との説もあるお玉(五代将軍・綱吉の生母)などがその一例である。
権力の座を射止めたとはいえ、庶民との接点をも排除しなかった春日局。そこから見えてくるのは、何やら親しみやすい人柄というべきだろうか。少々贔屓目に見てしまうのは、筆者だけではないだろう。

春日局生誕地とされるのが、丹羽市春日町黒井にある興禅寺。「お福産湯の井戸」や「お福の腰掛け石」などもある。/撮影:藤井勝彦
- 1
- 2